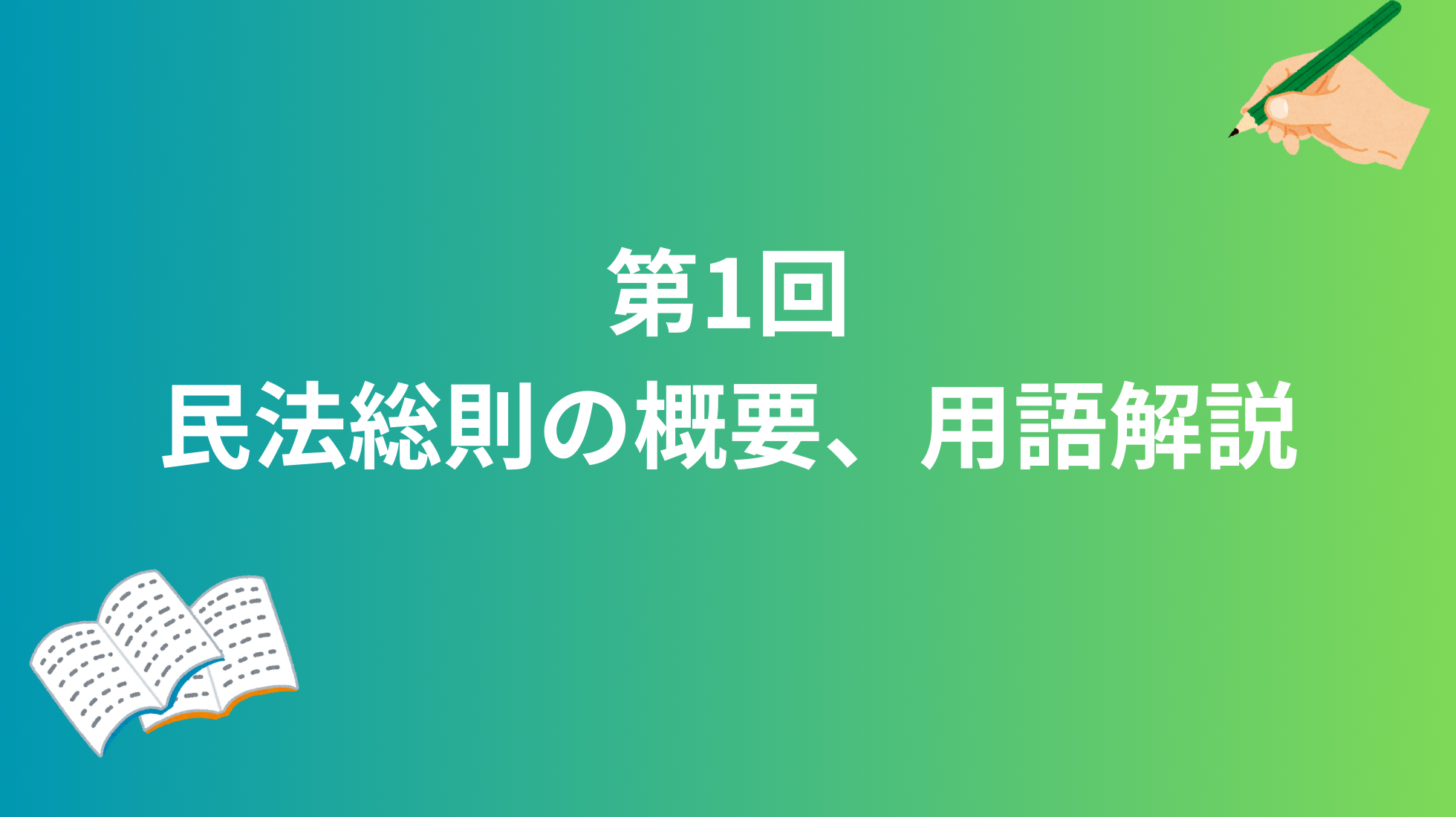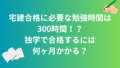「民法」が規律する範囲は非常に幅広く、覚えるべきこと・理解すべきことがとても多い科目です。
というのも、民法という法律は『人と物』『人と人』という関係をベースとした、日常生活のあらゆる活動についてルールを定めているからです。
そして民法の定め方・各条文の置き方は、【パンデクテン方式】と呼ばれる方法で記載されています。
数学で言えば「因数分解」のようなものです。
共通事項を前に置き、個別に定めるべき事項を後に置いています。
これから解説する「総則」は、民法を理解する上で欠かせない『共通事項』です。
「総則」の規定を常に念頭において、民法の細かい規定を見る意識を忘れないようにしましょう。
今回は「総則」の全体像と用語解説です。
では、始めていきましょう!
民法総則の全体像
民法総則は、民法全体に共通する基本原則を定める部分であり、第一編に位置づけられる。
構成は主に「通則」「人」「法人」「物」「法律行為」「期間の計算」「時効」に分かれる。
通則では私的自治・権利濫用禁止(1条3項)等を規定。
人では権利能力(3条1項)、行為能力制限制度(成年年齢18歳、未成年者取消権)などを定め、法人では社団法人・財団法人の成立要件を規律する。
物は法律関係の客体を定義し、法律行為は意思表示を中心に無効・取消・条件期限などを体系化する。判例上、心裡留保(93条ただし書)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)、詐欺・強迫(96条)が意思表示の典型問題となる。
期間計算は暦による方法を定め、時効は取得時効と消滅時効に大別され、判例上、権利行使の「障害事由」が議論される。
総則は民事関係全体の基礎規範として機能する。
私的自治・権利濫用
私的自治
私的自治とは、市民が自らの意思に基づき法律関係を形成できるという原則であり、民法の基本理念の一つである。
典型例は契約自由の原則であり、当事者は契約を締結するか否か、内容をどうするかを自由に決められる。
ただし、公序良俗(民法90条)や消費者保護法制、労働法などにより制限され、弱者保護や取引の公正が確保される。
判例も「契約自由は公共の利益に反しない範囲で認められる」としている。
権利濫用
権利濫用とは、形式的には権利の行使に見えても、その目的や態様が社会的相当性を欠き、信義則に反する場合には許されないとする原則である(民法1条3項)。
典型例として、嫌がらせ目的の土地明渡請求や報復的な訴訟提起がある。
最高裁も「権利の行使が専ら他人に損害を与えることを目的とする場合」などを権利濫用と認定している。
これにより、私的自治の限界が示され、権利行使に社会的妥当性が求められる。
権利能力
権利能力とは、権利を享有し義務を負担することができる地位をいう。
民法上「人は出生により権利能力を取得し、死亡によって失う」(民法3条)とされ、自然人は出生から死亡まで権利能力を有する。
胎児については例外的に、相続(886条)、遺贈(965条)、不法行為による損害賠償請求(721条)に関しては既に生まれたものとみなされる。
また、自然人以外に法人も権利能力を有し(33条)、権利義務の主体となる。
判例は、権利能力の内容は時代や社会の変化に応じて制約を受け得るとしつつも、その根本的保障は憲法上の人格権の基盤とも位置づけている。
行為能力
行為能力とは、単独で有効に法律行為を行うことができる資格をいう。
権利能力が「権利義務の主体となれる地位」であるのに対し、行為能力は自らの意思で有効な契約や法律行為を成立させる能力を指す。
原則として成年に達した者は完全な行為能力を有する(民法4条)。
一方、未成年者や成年被後見人は制限行為能力者とされ、保護者の同意を欠く行為は取り消し得る(民法5条・9条以下)。
成年被保佐人・被補助人については、一定の重要行為に限り同意権や取消権が認められる。
これらの制度は、意思決定能力に不十分さがある者を保護しつつ、取引の安全との調和を図るための仕組みである。
法律行為
法律行為とは、一定の法律効果の発生を目的とする意思表示を要素とする行為をいう。
民法における典型例は契約であり、当事者の合致した意思表示によって権利義務関係が生じる。
単独行為(遺言、代理権授与など)、双務契約(売買、賃貸借など)、多人数契約(組合など)に分類される。
法律行為の有効要件は①意思能力、②意思表示の存在、③内容の適法性(公序良俗違反でないこと・民法90条)、④方式の具備(書面など法定要件がある場合)である。
意思表示に瑕疵がある場合(錯誤・詐欺・強迫など)や制限行為能力者による場合には、無効または取消しの対象となる。
法律行為は私的自治を具体化する仕組みであり、取引関係を成立させる中心的な法的概念である。
意思表示
意思表示とは、一定の法律効果を生じさせる意思を外部に表現する行為をいい、民法における契約や法律行為の基本的要素である。
単なる内心の意思だけでは効力は生じず、社会に認識可能な形で外部に示されることが必要とされる。売買契約における申込みや承諾、署名押印などが典型例である。
意思表示の効力は、内心の意思と外部的表示が一致することを前提とするが、不一致や外部的な干渉がある場合には特別な規律が設けられている。
まず「心裡留保」(民法93条)は、真意ではないと知りつつ冗談などで行った表示であり、原則有効とされる。ただし、相手方が真意でないと知っていた場合には無効となる。
「虚偽表示」(94条)は当事者双方が通謀して行った真意と異なる表示で、無効とされるが、善意の第三者にはその無効を主張できない。
「錯誤」(95条)は事実や法律についての誤解に基づく意思表示であり、要件を満たすときは取り消しが可能である。
さらに「詐欺・強迫」(96条)は意思表示の自由を害する典型例である。
詐欺による意思表示は取り消しが可能であり、第三者による詐欺の場合は相手方が悪意または有過失でなければ取り消せない。
他方、強迫による意思表示は、畏怖により自由な意思決定が妨げられた場合で、相手方の善意・悪意を問わず常に取り消しが可能とされる。判例は「一般人ならば畏怖により自由意思を奪われる程度」であるかを基準とする。
また、意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じる(97条到達主義)。郵送や電信の例では、相手方の支配に入ったときに効力を持つと解され、最高裁は「通常到達すべき状態に置かれたときに到達とみなす」と判示している。
このように、意思表示は契約の成立・効力を支える根幹概念であり、意思と表示の不一致や外部的干渉に関する諸規定を理解することが、取引の安全と信頼を確保するうえで不可欠である。
代理
代理とは、本人に代わって他人(代理人)が法律行為を行い、その効果が直接本人に帰属する制度をいう(民法99条)。
代理が有効に成立するには、①本人の授与する代理権、②代理人による本人のためであることの表示(顕名)、③法律行為の適法性が必要である。
代理権の範囲を超えて行った場合は無権代理となり、本人の追認がなければ効力は生じない(113条)。
ただし、相手方が代理権があると信じた正当な理由がある場合には表見代理制度が働き、本人に効果が帰属することがある(109条以下)。
また、代理人は本人の利益を第一に考える義務を負い、自己契約や双方代理は禁止される(108条)。
代理制度は、取引の便宜と本人保護を調和させるための重要な仕組みである。
無効・取消し
無効とは、法律行為が初めから効力を生じない状態をいい、公序良俗違反(民法90条)や通謀虚偽表示(94条)などが典型である。
無効行為は当然に効力を持たず、誰からでも主張でき、追認によって有効化することもできない。
一方、取消しは、一応は有効に成立した法律行為を、後から取り消すことによって初めから無効であったかのようにする制度である(民法121条)。
制限行為能力者の法律行為や、錯誤・詐欺・強迫による意思表示などが対象となる。
取消権者に限って主張でき、追認すれば有効に確定する点が無効との違いである。
両者はいずれも私的自治の限界を示す制度として、取引の安全と個人保護の調整を担っている。
時効
時効とは、一定期間の経過によって法律関係を確定させる制度であり、取得時効と消滅時効に大別される。
取得時効は、他人の物を一定期間占有した者がその所有権を取得する制度で、所有の意思をもって平穏かつ公然に占有した場合、善意無過失なら10年、悪意でも20年で取得できる(民法162条)。
消滅時効は、権利を一定期間行使しないとその権利が消滅する制度で、原則として債権は権利行使できる時から5年、または権利発生から10年で時効により消滅する(166条)。
時効の完成は権利者の地位を害するため、援用が必要であり、時効完成を知られても自動的には効力を生じない。
時効制度は、権利関係を安定させ、長期にわたる紛争を防ぐ役割を担う。